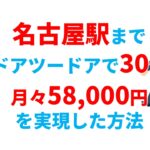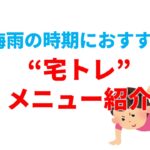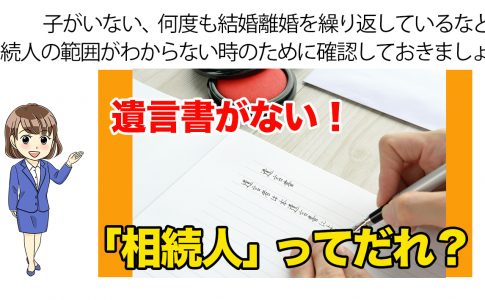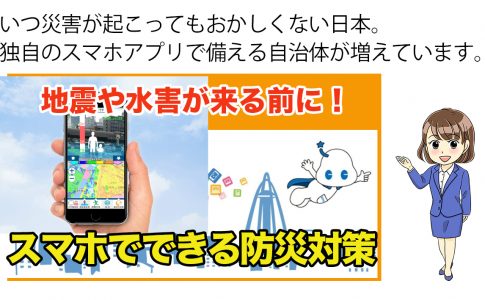離婚後の親権を両親に認める「共同親権」の導入を盛り込んだ民法改正案が可決されたことで、2026年までに制度が施行される見通しとなりました。
この記事では、共同親権とはどういった仕組みなのか、また共同親権の導入でどのようなメリット・デメリットがあるのかといった点を解説していきます。
離婚後の親権に関する各国の対応・制度も紹介しているので、合わせて参考にしてみてください。
共同親権とは?現在の親権制度との違い
まずは、現在の日本における親権制度の概要と、共同親権の仕組み・違いについて詳しく見ていきましょう。
日本における親権制度
そもそも親権とは、親が未成年の子どもを健全な一人前の社会人として養育保護する権利・義務のことです。
現在の日本では、婚姻中の父母については双方が親権者となる一方、離婚後は父母のどちらか片方のみを親権者に指定する「単独親権」が採用されています。
父母のどちらが親権者となるのかについてはケースバイケースで、その親子を取り巻く様々な事情を総合的に比較して、より“子どもの利益”になると判断された方に親権が与えられる仕組みです。
なお平成30年の調査では、離婚後に父親が親権者となったケースが11.9%、母親が親権者となったケースは84.5%でした。
導入が予定されている「共同親権」とは
2026年までに導入予定となっている「共同親権」は、婚姻中だけでなく離婚後も父母の双方が親権者となって子どもを養育保護できるようにする制度です。
共同親権となった場合、子どもに関する重要な選択(進学や転居等)を行う際に父母間での話し合いが必要となります。
なお共同親権が導入されたからと言って必ずしも共同親権になるわけではなく、父母間の協議によって単独親権または共同親権の選択が可能になるという仕組みです。
また共同親権の状態であっても、日常生活(食事・習い事等)や緊急事態(ケガによる手術等)の判断はどちらか一方の親が単独で行えます。
共同親権の導入に伴うメリット・デメリット
続いて、共同親権の導入で期待されるメリットと、対策が必要な課題・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
共同親権のメリット
共同親権の主なメリットとして、以下のような点が挙げられます。
親権争いの回避・抑制
現行法では、未成年の子どもがいる父母が離婚する際、どちらか一方を親権者に指定しなければなりません。
そのため、父母の双方が子どもの親権を希望した場合に、離婚の合意に至らず調停や裁判が長期化してしまうケースも少なくないのです。
共同親権が導入されればこうした親権争いを防げるため、離婚成立までのハードルが低くなり、父母および子どもへの精神的なストレスの軽減も見込めるでしょう。
面会交流の円滑化
共同親権で父母の双方が親権を得た場合、離婚後もお互いに協力して子育てを行うことが“義務”となります。
これにより、子育ての負担がどちらか一方に偏ることを防いだり、面会拒否等で子どもに会えなくなるリスクを回避したりできるというメリットを見込めます。
また仮にこうしたトラブルが生じた場合でも、話し合いに参加する権利や面会する権利をより強く主張できるようになるでしょう。
養育費の滞納防止
共同親権を導入することで、養育費の未払い・滞納トラブルを防止できるというメリットもあります。
例えば、親権者が面会交流を拒否し、子どもと離れて暮らす親が子どもと会えないという状況が続くことで、養育費の支払いに対するモチベーションが低下して滞納に繋がるというケースは珍しくありません。
共同親権によって子どもとの面会交流が円滑化すれば、“子どものために養育費を支払っている”という感覚が強まるため、未払い・滞納が減少すると考えられています。
共同親権のデメリット・課題
一方で、共同親権の導入には以下のようなデメリット・課題も存在します。
DVや虐待の被害が継続するリスク
DVや虐待の加害者と関係を継続しなければならないという点は共同親権における大きな課題の1つです。
改正案では、DVや虐待等があったと認められるケースについて、共同親権ではなく単独親権を選択することが明記されていますが、裁判所がどのような基準で認定するのかといった点はまだまだ議論が必要です。
また共同親権の運用までに、行政や福祉サービスをどこまで整備できるのかという点も課題となっています。
両親の対立による精神的ストレス
共同親権によって父母の双方に親権が与えられる場合でも、離婚後は基本的にどちらか一方の親が子どもと生活することになります。
しかし子どもに関する重要な選択(進学や転居等)を行う際は双方の話し合いで意思決定する必要があるため、父母間の行き来や意見の対立によって子どもに精神的ストレスがかかる可能性がある点は懸念事項の1つです。
海外における親権制度の導入状況
最後に、海外における親権制度の現状を見ていきましょう。
法務省が平成31年に実施した調査によると、諸外国における親権制度の現状は以下の通りとなっています。
| 単独親権のみが導入されている国 | インド、トルコ |
| 共同親権も導入されている国 | アメリカ(ニューヨーク州、ワシントンDC)、カナダ(ケベック州、ブリティッシュコロンビア州)、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、インドネシア、韓国、タイ、中国、フィリピン、イタリア、イギリス(イングランド及びウェールズ)、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、ドイツ、フランス、ロシア、オーストラリア、サウジアラビア、南アフリカ |
上表から、諸外国においては共同親権を認めている国が多数派であることが分かります。
ただし、共同親権の内容は国によって違いがあり、主な例として以下のようなものが挙げられます。
- カナダ、スペイン等:父母の協議により単独親権・共同親権を選択できる
- インドネシア:養育している親が子どもに関する事項を決定するのが基本(共同での親権行使は稀)
- イギリス、南アフリカ:父母のいずれもがそれぞれ単独で親権を行使できる
- ドイツ:著しく重要な事項の決定には父母の同意が必要となるものの、日常に関する事項は同居する親が単独で判断できる
- メキシコ:共同で行使するのは財産管理権のみで、監護権についてはどちらか一方の親が行使できる 等
まとめ
民法改正までにはまだ時間がありますが、現在離婚を検討中の方は最新情報に注目しておいた方が良いでしょう。
親権者の選定で合意を得られずにいる方や、養育費の未払い・滞納で悩んでいる方は、一度弁護士等の専門家に相談してみることをおすすめします。