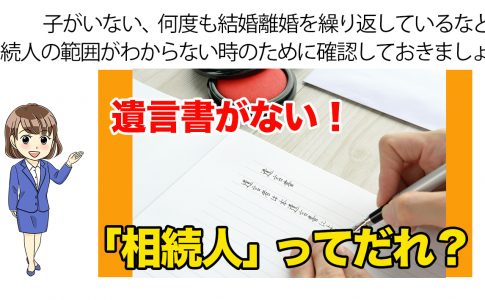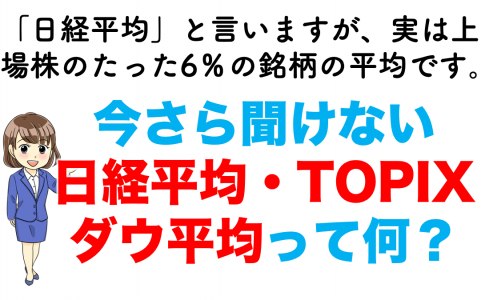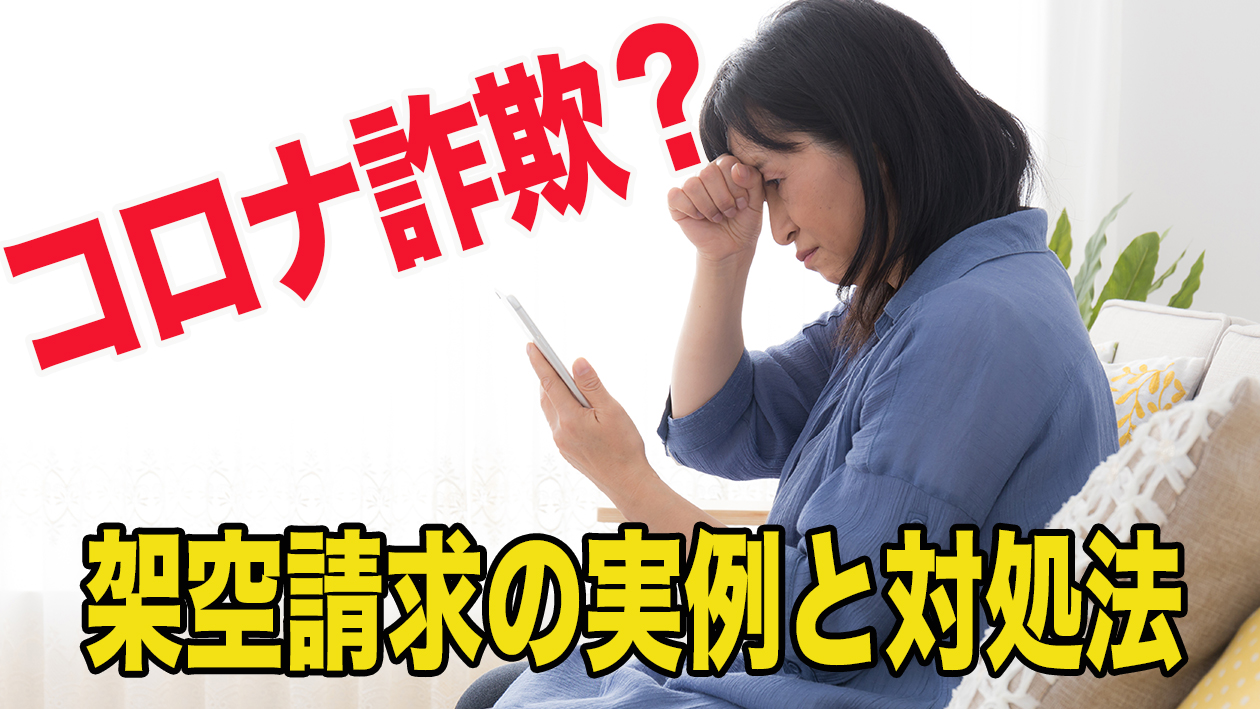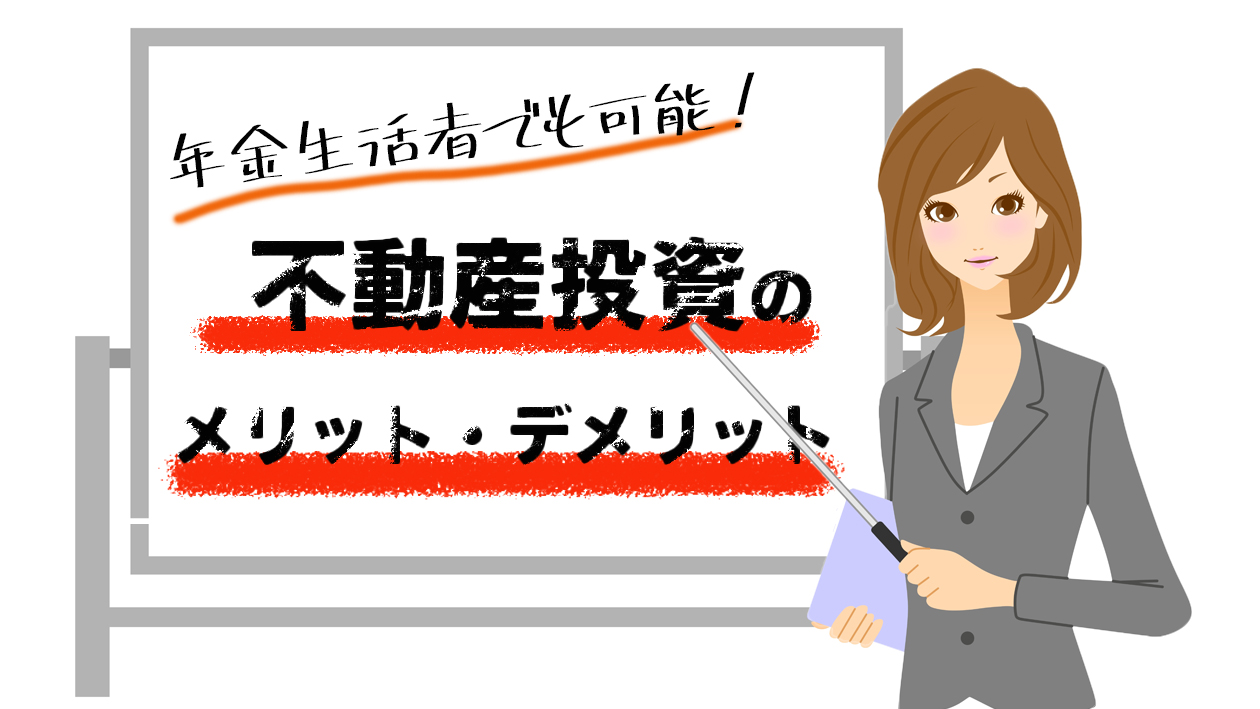近年、低金利時代が続いていた日本経済ですが、2024年に入り日銀はついに利上げを決定しました。これにより、市場や税金、住宅ローン金利など、不動産業界にも大きな影響が出る可能性があります。
利上げは、金融政策の正常化に欠かせない措置ですが、景気の回復を示す反面、将来の景気低迷も示唆しているわけです。
本記事では、利上げの意味や不動産市場への影響、さらに相続税対策や住宅ローン(投資ローン)金利にどのような変化や対応が必要かを詳しく解説します。
景気が上昇傾向にある今こそ、将来を見据えた戦略的な資産運用が重要です。
| 【この記事で分かること】 ・利上げの概要、密接に関わる不動産への影響について解説しています。 ・相続税対策として大きな影響はありませんが、それ以上に考えるべき重要なこととは何でしょうか。 ・利上げにおける居住用不動産(マイホーム)、賃貸用不動産(投資)の在り方とは? |
日銀が利上げを発表、そもそも利上げとは?

日本銀行は、長い間続いていた低金利政策から転換し、先日利上げを発表しました。これは日本経済にとって大きな転換点であり、特に不動産市場や金融商品への影響が懸念されています。
本章では、利上げの基本的な意味と、その背景にある要因を解説し、今後予想される不動産市場への影響について考察します。
利上げの意味
利上げとは、日本中央銀行(日銀)が政策金利を引き上げることで、貸出金利が上昇し、経済全体の資金調達コストが高まる現象のことです。
通常、景気が過熱してインフレリスクが高まる際に、経済のバランスを取るために行われます。
日銀による利上げ決定の背景には、新型コロナウイルスで低迷した景気に回復の兆しが見られること、そしてインフレによる物価上昇への抑制が考えられます。
これにより、段階的に住宅ローンや投資ローンの金利上昇が考えられるでしょう。
利上げがもたらす不動産市場への影響
「利上げ」と「不動産」は非常に密接な関わりを持ち、不動産市場への影響はとても大きいものです。
まず、住宅ローン金利が上昇することで、住宅購入希望者の借入へのハードルが高くなり、住宅市場が冷え込む可能性があります。そして、過去の傾向では、冷え込んだ市場を回復させるために、不動産価格が下落していきます。
少子高齢化による人材不足や建材費の高騰により、もしかすると過去のように著しい価格下落は見られないかもしれません。
万一そうなると、利上げにより単純に投資物件の利回りが低下し、不動産投資の魅力が減少することも考えられます。
円安で増えている外国人投資家たちの動向も注目していきたいところです。
利上げは相続税対策に影響する?今考えるべきことは
利上げによって、相続税対策に打撃となるような直接的な影響はありませんが、間接的な変化は考えられます。
利上げは景気が好転している兆しでもありますが、今後の経済状況や金利の動向を見据えた戦略が必要です。
以下では、利上げが相続税対策に与える間接的な影響について解説します。
利上げによる相続税の直接的な影響はあまりない
まず、利上げが相続税そのものに直接的な影響を与えることは、ほとんどありません。
相続税は、相続財産の価値(評価額)に基づいて課税されるため、利上げで即座に税額が変動することは考えづらいです。
ただし、利上げによって不動産価格が下落すれば、相続税の評価額が低くなり、税負担が軽減されることは考えられます。
景気が良い時期こそ先を見据えるべき
利上げは景気の好転を示すものですが、景気は常に循環します。
今が好景気に向かっているからこそ、将来の不景気を見越した対策を講じることが重要です。
例えば、不動産価格が高騰している現況を活かし、物件の売却を検討するのも1つの手です。また、しっかりと戦略が描けていれば、売却資金で新たに別の不動産を購入するのも良いでしょう。
2024年8月現時点で、変動金利に大きな変化は発表されていません。
しかし、金利が上がり切ってからでは、不動産価格の下落が始まってしまい、高値売却は期待できないかもしれません。
住宅ローンの選択肢とリスク管理
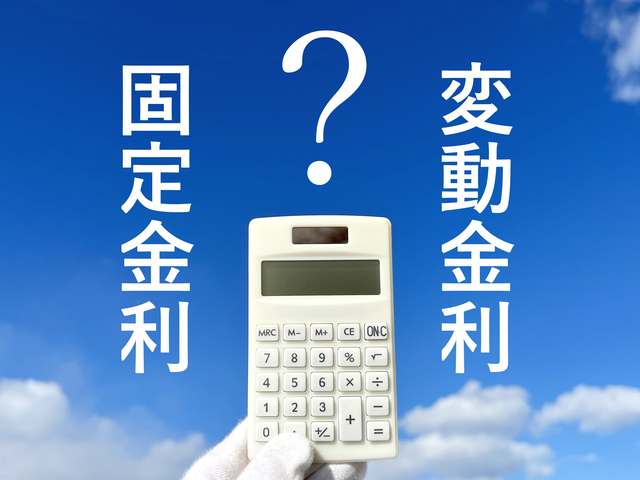
利上げに伴い、これから住宅を購入する人は、住宅ローンの選択も慎重に行う必要があります。
まずは、変動金利と固定金利、それぞれのメリットとデメリットを理解しましょう。
そして、将来のリスクを長期的な視野で考慮したうえで、最適な選択が必要です。
変動金利と固定金利の選択
住宅ローンを選ぶ際、「変動金利」と「固定金利」のどちらを選ぶかは、とても重要なポイントです。
これまで続いた金融緩和政策では、変動金利は低金利の恩恵を大きく受けることができ、月々の返済額が少なくなるメリットがありました。
しかし、金利の上昇が見込まれる今後は、返済額が増加するリスクがあります。果たしてどこまで上昇するのか、その上限が分からない点が最大の悩みどころでしょう。
一方で、固定金利は契約時の金利が返済期間中ずっと変わらないため、将来的な金利上昇の影響を受けず、返済額が安定します。
利上げの局面では、固定金利の方が安全性は高いと考えられますが、その分初期の返済負担や結果的に総返済額が高くなる可能性があります。
長期的な視野でのリスク管理
住宅ローンの選択にあたっては、短期的な金利動向だけでなく、長期的な視野でのリスク管理が重要です。
特に、ファミリー世帯は子供の成長につれて将来の支出増加を考慮し、無理のない返済計画が求められます。
また、固定金利が高くても、安心感を優先するために選択する価値はあります。毎月同じ返済額なので、利上げに一喜一憂しない精神的なメリットは大きいです。
家族の生活を守るためにも、利上げに対して慎重にローンを検討しましょう。
アパート所有者は売却して現金化を検討するべきか?
不動産投資をする人にとって、利上げは致命傷になり得ます。
利上げによって、ゆくゆく投資ローンの金利が上昇することで、キャッシュフローの悪化は免れません。特に、土地と建物の1棟ものを所有するオーナーは、今後の投資戦略を見直す必要があります。
本章では、利上げによるアパートの売却についての考え方や、土地活用について解説します。
アパート売却も戦略の1つの候補
アパートを所有している場合、利上げによって不動産価格が上昇しているタイミングで売却し、現金化することを一度検討してみてください。
特に、少子高齢化や時代の流れによる家族構成の変化に伴い、今後の需要が見込めない物件は、早めに売却することでリスクの軽減を図れるでしょう。
もちろん、景気は循環するので、利上げで不動産価格が下がったとしても、いずれはまた高騰するタイミングが訪れるはずです。
しかし、その時には物件の築年数も古くなっていますので、思い通りの金額で売却できなかったり、買主の融資付けに苦労したりと別の問題が出る可能性があります。
現金化した資産を他の投資先に再配分することで、安定した資産運用が可能になります。
土地活用で賃貸住宅を建てるのも1つの手
利上げ要因以外にも、昨今の不安定な日本経済に加え、未婚率の増加や老後不安などで、今後持ち家派が減少する可能性は無視できません。
そのため、一部のエリアでは、賃貸需要への高まりが予想されます。
すでに土地を所有している場合、エリア次第でアパートやマンションを建設し、安定した家賃収入を得るのも1つの手です。
ただし、利上げにより、建築コストや借入コストが上昇する可能性があるので、時期や詳細の見積もりなど資金計画が非常に重要になります。
いずれにしても、利上げが不動産にもたらす影響は大きく、利上げによる市場の変化が起こる前に動き出すことがポイントです。
まとめ
2024年の日銀利上げは、不動産市場や借入に影響を与える可能性が高く、特に住宅ローン、投資ローンを抱える方々は注意が必要です。
相続税対策には直接的な影響は少ないものの、マイホームにしても投資物件にしても、不動産価格の変動を見据えた資産管理が重要です。
住宅ローン選びでは金利上昇リスクを理解し、将来を見据えた長期的な計画を立てましょう。また、不動産オーナーは、所有物件の売却や土地活用の戦略を見直すことが求められます。
利上げによる市場の変動を見越した上で、今のうちに戦略を立て、早期に動き出すことがとても大切です。