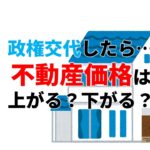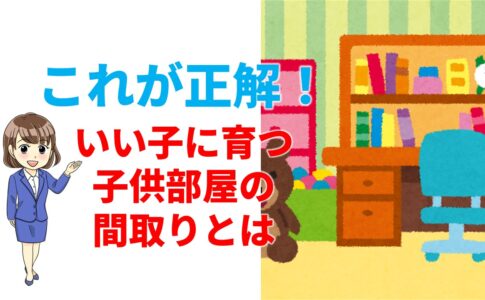最近、広い敷地を持つ一軒家で、余ったスペースを有効活用する方法として「離れ」を建てることが人気です。趣味の空間やゲスト用の宿泊スペース、さらには在宅ワークのためのオフィスなど、離れには多彩な使い道があります。
しかし、実際に建てる際には、費用や法律面に注意が必要です。
本記事では、「離れ」の魅力や具体的な活用法、そして建築時に押さえておくべきポイントを詳しく解説していきます。
| 【この記事で分かること】 ・離れの定義や魅力、作り方が分かります。 ・建築時の主な7つの注意点をまとめています。 ・離れで考えるべき費用項目と工期目安を解説しています。 |
離れの定義
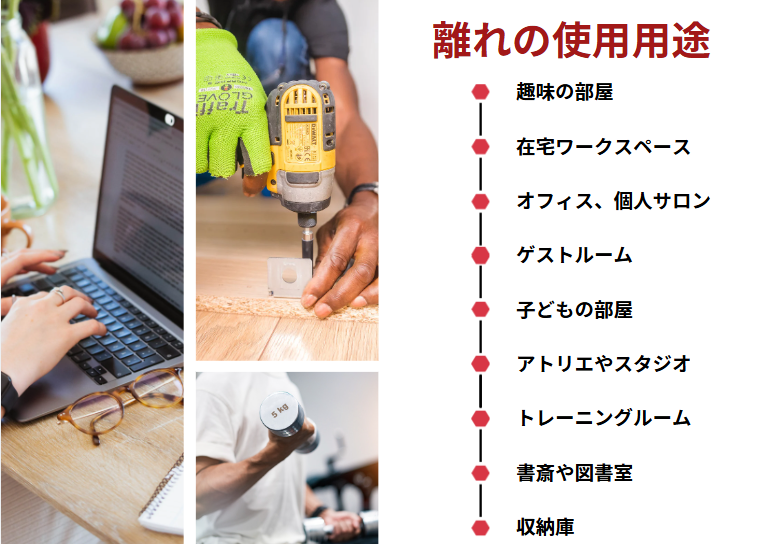
「離れ」とは、母屋と同じ敷地内にあり、離れた場所に建てられる別棟のことを指します。建築基準法では、基本的に「1つの敷地には1つの住宅しか建てられない」というルールがありますが、いくつかの条件を満たせば「離れ」として建築することが可能です。
離れを建てる際に重要なのは、母屋に付属する建物であることを示すことです。例えば、キッチンやトイレ、浴室など、生活に必要なすべての水回り設備を備えた建物は、新たな住宅とみなされるため、建築できません。
しかし、これらの設備が一部欠けている場合には、離れとして認められる可能性があります。したがって、離れを建築する際には、建築基準法に違反しないよう、住宅としての完全な機能を持たない付属的な建物として計画する必要があります。
離れの魅力
「離れ」が人気を集める理由には、どんな魅力があるからなのでしょうか。
以下で、具体的なポイントを見ていきましょう。
母屋と同じ敷地内に建っている
「離れ」の大きな利点は、母屋と同じ敷地内に建設できることです。
離れを居住空間の一室として使う場合、個人のプライバシーを確保することができます。例えば、親戚の子が大学に通う際、通学に便利な下宿先として活用することも可能です。
さらに、居住空間以外の活用方法も魅力的です。離れを大きな収納庫として使用することで、家全体の収納スペースを拡張したり、工具や作業用品を収納したりするワークスペースとしても機能し、生活の利便性がさらに向上します。
使用用途が豊富である
離れの魅力は、何と言ってもその多彩な使用用途にあります。
敷地内にもう一つの空間があることで、家族のライフスタイルに合わせたさまざまな活用が可能です。
使用用途が多彩だからこそ、個人の趣味や家族の成長に伴い、必要に応じた使い方ができるのも大きなポイントです。
- DIYなど趣味の部屋
- 在宅ワークスペース
- 個人サロン、オフィス
- ゲストルーム
- 子どもの遊び部屋、勉強部屋
- アトリエやスタジオ
- トレーニングルーム
- 書斎や図書室
- 収納庫
このように、離れは家族のニーズ、ライフスタイルに合わせたフレキシブルな空間を実現してくれます。
離れを作る流れ

| 手順 | 具体的にやること |
| ①建築条件を確認する | 敷地の建蔽率や容積率、その他の制限を確認し、離れを建てるスペースがあるかを確かめます。分からない場合は、管轄の役所で確かめることができます。 |
| ②用途や目的を明確にする | 離れの使用目的をしっかりと考えましょう。趣味の部屋にするのか、ゲストルームとして活用するのか、プランニングによって広さや作り方が異なります。 |
| ③リフォーム会社を探す | 職人の腕にも技術の差があるため、実績が豊富な会社を選びましょう。信頼できる会社を選ぶためには、過去の施工事例やお客様の口コミなどを参考にすることが大切です。 |
| ④見積もりを依頼する | 複数の会社にプランと見積もりを依頼します。その際、予算や希望する設計内容をしっかりと伝え、同じ条件で比較検討できるようにします。オプション費用なども細かく確認しましょう。 |
| ⑤請負工事契約をする | 費用や見積もりに納得できたら、契約を進めます。総額だけでなく、補償内容や工期についても確認し、万が一のトラブルに備えられるかどうかを確認しましょう。 |
| ⑥建築確認申請を行う | リフォーム会社に依頼して、建築確認申請を代行してもらいます。建築確認申請は、竣工後も大切に保管しましょう。 |
| ⑦近隣への挨拶を行う | 工事開始前に、近隣住民に挨拶し、工事の内容や期間を説明します。一般的には工事業者が代行して行います。 |
| ⑧工事の着工と竣工 | 工事中も進捗を確認し、不安があれば都度確認しましょう。 |
| ⑨表題変更登記をする | 竣工後、1ヵ月以内に表題変更登記を行います。固定資産税の評価にも影響するため、早めの手続きを推奨します。 |
※建蔽率:敷地に対する建物の占有面積割合
※容積率:敷地に対する建物の延床面積割合
離れを作るときの7つの注意点

離れを作る際には、法的なルールや実際の使い勝手についても慎重に考える必要があります。そこで、失敗しないために押さえておきたい7つの注意点を紹介します。
1.建築基準法に基づく離れの条件を確認する
離れを建てる際には、建築基準法に従わなくてはなりません。はじめに、敷地の建蔽率と容積率を確認し、建築可能な建物の面積を正確に把握することが必要です。
また、地域によっては景観や周辺環境を守るため、高さや日影に関する制限が設けられていることがあります。他にも、建築予定地が防火地域や準防火地域に指定されている場合、使用する建材に厳しい防火基準が設けられている可能性があります。
これらの細かい規制を遵守しないと、建築許可が得られないことがあるため、事前の確認が重要です。
2.母屋が違法建築物だと離れは建築できない
母屋自体が建築基準法に違反している場合、離れを建てることができません。違法建築物として認定されている建物に対しては、増築や新たな建物の建設が許可されないためです。
特に古い建物では、当時の基準では問題なかったとしても、現行の基準では違法とされるケースもあります。
3.渡り廊下の仕様制限に注意する
離れと母屋をつなぐ渡り廊下を設置する場合、その仕様に注意が必要です。渡り廊下のデザイン次第で、建物全体の扱いが変わり、敷地の建蔽率や容積率の制限がかかる可能性があります。
- 屋根も壁もない場合
渡り廊下に屋根も壁もない場合、デッキやテラスと同じように、建物の床面積には含まれません。そのため、比較的自由に設置できることが多いです。
- 屋根のみあり、壁がない場合
この場合は、外気に開放された空間と見なされ、床面積に算入されないことが一般的です。ただし、この扱いは地域によって異なることがあるため、しっかり確認しましょう。
- 屋根と壁がある場合
屋根と壁で囲まれた渡り廊下は、建物として認定されます。この場合、母屋や離れと同じように建物の床面積として算入され、敷地の建蔽率や容積率に影響します。
建築スペースに制約がある場合は、規定に配慮した設計が求められます。
- 母屋との一体扱いになる場合
渡り廊下が屋根と壁で囲まれている場合、母屋と離れが一体の建物として見なされることがあります。この場合、二世帯住宅のように水回り設備があっても問題はありませんが、面積の制限がかかります。
4.建築確認申請が不要な場合もある
離れを建てる際、通常は建築確認申請が必要ですが、規模や用途によっては申請が免除されることがあります。
例えば、離れの床面積が10平方メートル以下であり、トイレや台所、浴室などの水回りが揃っていない場合、建築確認申請を提出しなくても良いケースがあります。また、防火地域や準防火地域外であり、都市計画区域外の場合も、申請が不要となることが多いです。
ただし、申請が不要だからといって、法的な規制を全く無視して良いわけではありません。
5.水回り設備をすべて設置しようとしない
離れを住宅として認められないようにするために、キッチンやトイレ、浴室などの水回り設備をすべて設置しないことが基本的なルールです。水回りが完全に揃ってしまうと、離れが独立した住宅とみなされ、母屋とは別の建物として扱われるため、建築基準法に触れる恐れがあります。
従って、たとえばキッチンや浴室のどちらか一方を設置しないなど、あくまで母屋に付属する建物としての計画が求められます。
6.固定資産税が増額する
離れを建築すると、その分固定資産税が増額する可能性があります。新たに建てた建物が評価され、母屋と合わせて課税対象となるためです。
特に、離れが広い規模や資産性の高い仕様で建築された場合、税額が大幅に増えることがあります。
7.表題部変更登記を忘れずに行う
離れを建築した後は、1カ月以内に表題部変更登記を行う必要があります。これは、新たに建てた建物を法的に登記する手続きであり、これを行わないと法的に建物が存在しないとみなされてしまいます。
将来的な売却や相続時に大きなトラブルを避けるためにも、忘れないようにしてください。表題部変更登記を行うことで、固定資産税や保険などの手続きも円滑に進めることができます。
離れの建築費用と工期
最後に、離れの建築にかかる具体的な費用と工期の目安について解説します。
必要になる費用
離れの建築費用は、規模や使用する材料、設備の内容によって大きく変わります。一般的には、シンプルな構造(小規模な木造)であれば数百万円からが相場です。
以下に、必要となる主な費用項目をまとめました。
- 設計費用:建築士に建物の設計を依頼する費用で、設計の複雑さによって変動します。
- 建築費用:基礎工事や外装、内装、屋根などの建設にかかる費用です。材料や設備の選定によって費用が上下します。
- 設備費用:水回りや電気配線、空調設備など、生活に必要な設備の導入費用が含まれます。特に、キッチンや浴室などを設置する場合は、配管工事なども必要となるため、費用がかさむ傾向にあります。
- 確認申請、登記費用:建築確認申請や、竣工後の登記にかかる手数料も見積もっておきましょう。
材料費や人件費が上昇している状況下において、後から費用の手出しがないよう、多めに見積もっておくことがポイントです。
工期の目安
離れの建築にかかる工期は、建物の規模や構造によって異なりますが、一般的には2〜4ヶ月程度が目安です。以下の工期の流れを参考にしてみてください。
- 設計・準備期間(約1ヶ月)
- 基礎工事(約2〜4週間)
- 建物本体の工事(約1〜2ヶ月)
- 最終調整・検査(約1〜2週間)
工事の進行状況や天候によっても工期は前後する可能性があります。余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
まとめ
「離れ」は、家族のライフスタイルに合わせてさまざまな活用ができる魅力的な空間です。趣味の部屋や在宅ワークスペースだけでなく、収納やトレーニングルームとしても利用でき、暮らしの幅が広がります。
ただし、建築には法的な規制やコスト、手続きの確認が必要なため、しっかりとした事前準備が必要です。これらを踏まえて計画を進めることで、理想的な「離れ」のある生活を実現できるでしょう。
もし、すぐに「離れ」のある暮らしを始めたい方には、こちらの物件がおすすめです。
本物件は新築住宅と同じ敷地内にすでに「離れ」が作られているため、引っ越したその日から快適な空間を楽しむことができます。
自分のライフスタイルに合わせた新しい暮らしを、ぜひ実現してみませんか。


東郷町諸輪
(販売が終了している場合があります)