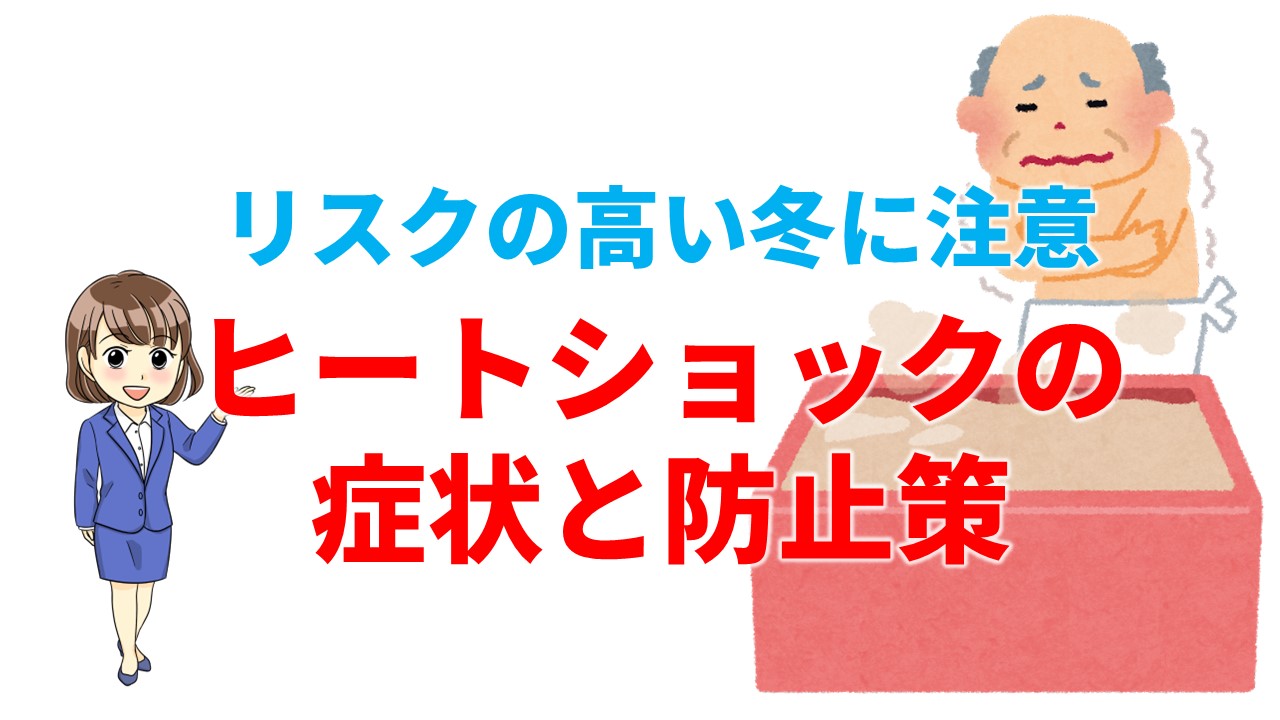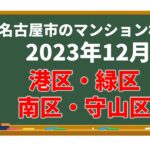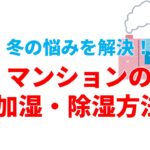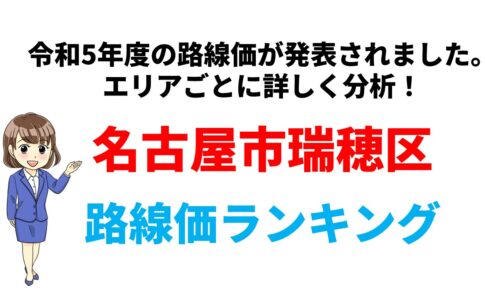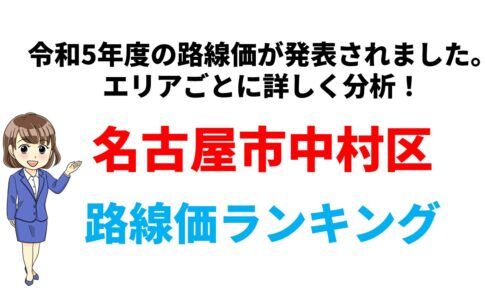11月~4月頃の寒い時期を中心に、暖かい部屋と寒い部屋との“温度差”が原因となって引き起こされる「ヒートショック」による事故が多発します。
この記事では、ヒートショックの主な症状と起こりやすい人の特徴について解説していきます。
ヒートショックを防ぐための対策もまとめているので、特に高齢者の方が身近にいるという方はぜひ参考にしてみてください。
ヒートショックとは?
まずはヒートショックのメカニズムと発生しやすい場所・状況について詳しく見ていきましょう。
ヒートショックのメカニズム・症状
ヒートショックとは、暖かい部屋と寒い部屋との温度差による急激な血圧変動が引き起こす健康障害のことです。
具体的なヒートショックのメカニズムは以下の通りです。
- 暖かい部屋から寒い部屋に移動する際、体温の低下を防ぐために体を震わせて熱を発生させる
- 発生した熱を体内に留まらせるため、血管を収縮させて血液の流れを遅らせる(血圧が上がる)
- 再び暖かい部屋へ移動した際に、収縮した血管が拡張する(血圧が急降下する)
このように、血圧の乱高下によって心臓や血管に大きな負荷がかかると、めまいやふらつきといった症状が発生し、その場で転倒したり意識を失ったりするリスクも高まります。
また脳梗塞・脳卒中・心筋梗塞等の疾患を引き起こす可能性もあるため、気温差が大きくなりやすい冬場は特に注意が必要な健康障害の1つです。
ヒートショックが発生しやすい場所
ヒートショックが発生しやすい場所・状況として、以下のようなケースが挙げられます。
- 冬の朝、暖かい布団から出るときや寝室から移動するとき
- ゴミ捨て等でちょっとした外出を行うとき
- お風呂に入るとき
- 夜間・早朝にトイレへ行くとき 等
ヒートショックは冬場の浴室・洗面所・トイレ等で特に起こりやすいと言われています。
浴室やトイレは人目に付きにくく、発見が遅れがちになるため日頃から注意しておく必要があるでしょう。
ヒートショックを起こしやすい人
ヒートショックは誰にでも起こる可能性がある健康障害ですが、中でも以下の条件に該当する方は発症リスクが高いため注意が必要です。
- 65歳以上の高齢者
- 狭心症や心筋梗塞等の疾患にかかった経歴がある
- 不整脈・高血圧・糖尿病・動脈硬化等の持病がある
- 食後・飲酒後に入浴する習慣がある
- 1番風呂や熱め(42度以上)のお湯に浸かる習慣がある
- 浴室や脱衣所に暖房機器が設置されていない
- リビングと浴室やトイレとの距離が離れていて暖房が行き届いていない 等
心臓や血管が弱っている高齢者の方や、すでに病歴や持病のある方等は血圧変動の影響を受けやすく、ヒートショックを起こしやすい傾向にあります。
また食後や飲酒後は血圧が変動しやすい状態となるため、夕食後に入浴する習慣があるも注意が必要です。
ヒートショックを防ぐためのポイント
続いて、ヒートショックの発症リスクを減らすためのポイントと、万が一ヒートショックが起きてしまった場合の対処法について詳しく見ていきましょう。
ヒートショックの予防方法
ヒートショックの主な予防方法として、以下の対策が挙げられます。
| 予防方法 | ポイント |
| 暖房設備を設置する | 脱衣所やトイレ等の気温が下がりやすい場所にヒーターを設置することで、リビングとの寒暖差を緩和する効果が見込めます。 |
| 入浴前後に水分をとる | 入浴中は汗をかくことで体内の水分が減少するため、血液がドロドロになりがちです。入浴前後にコップ1杯の水を飲み、サラサラの状態を維持するようにしましょう。 |
| 入浴前後の食事・飲酒は避ける | 食後は消化器官に血液が集中するため、血圧変動が起こりやすくなります。なるべく食事前に入浴を済ませ、30分程度時間をあけてから食事を始めるのがおすすめです。 |
| お風呂の温度は41度以下に設定 | 42度以上のお風呂は血圧が一気に低下するため、41度以下に設定するようにしましょう。また長湯もヒートショックの要因となるため、10分以内に上がることが推奨されます。 |
| 一人での入浴を避ける | ヒートショックが発生した場合、発見が遅れることで命にかかわる危険性があります。なるべく家族の在宅中に入浴し、入浴の前に一声かけるといった工夫をするのが大切です。 |
ヒートショックが起きたときの対処方法
家族がヒートショックの状態になってしまった場合は、速やかに以下の対応を行いましょう。
浴槽で意識を失っていた場合は、浴槽のお湯を抜いて引き上げる
- 呼びかけへの応答がない場合や呼吸が弱い場合は救急車を呼ぶ
- 脈や呼吸を確認できない場合は、救急車を呼んだ後応急処置(胸骨圧迫・人工呼吸)を施す
- 頭を打った場合は、嘔吐で異物が喉につまる可能性があるため頭を横向きにしておく
まとめ
冬場は居住空間と浴室・トイレ等との温度差が大きくなりやすいため、血圧の乱高下によるヒートショックのリスクが高まります。
特に高齢者の方や持病のある方は発症リスクが高いため、普段から暖房を設置したり食事のタイミングに気を付けたりしてヒートショックから身を守ることが大切です。