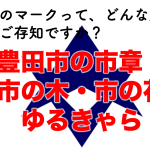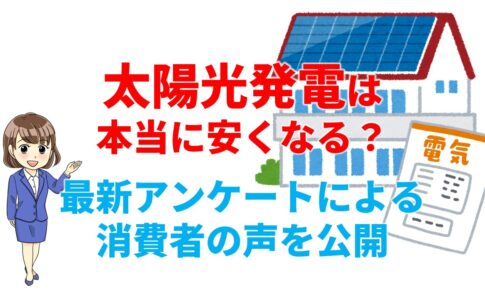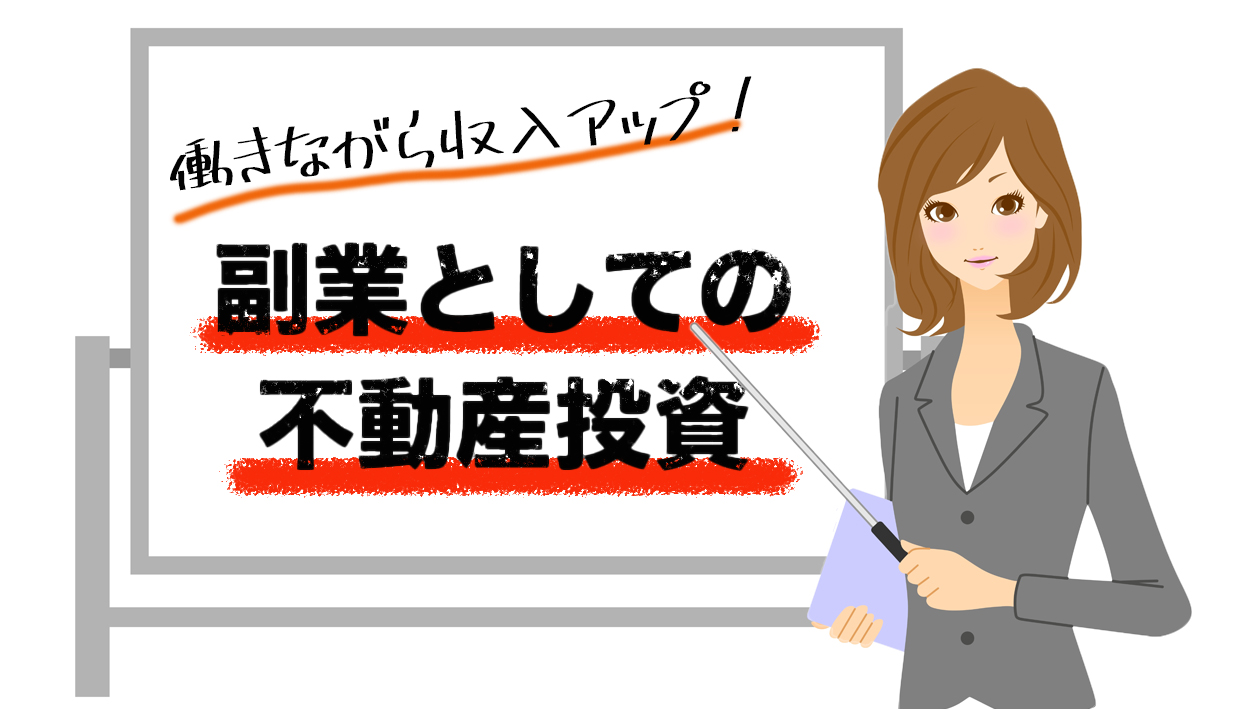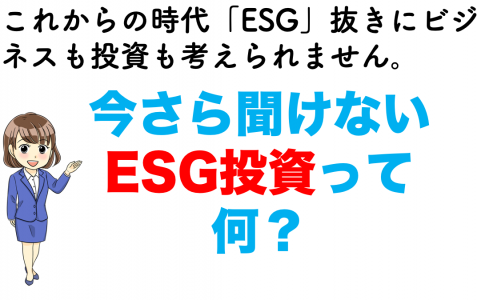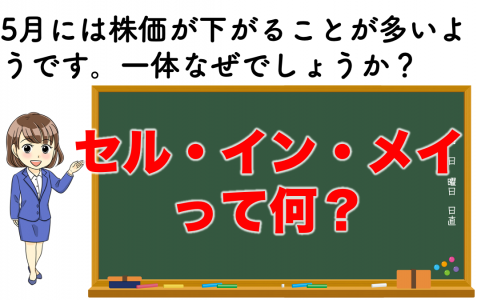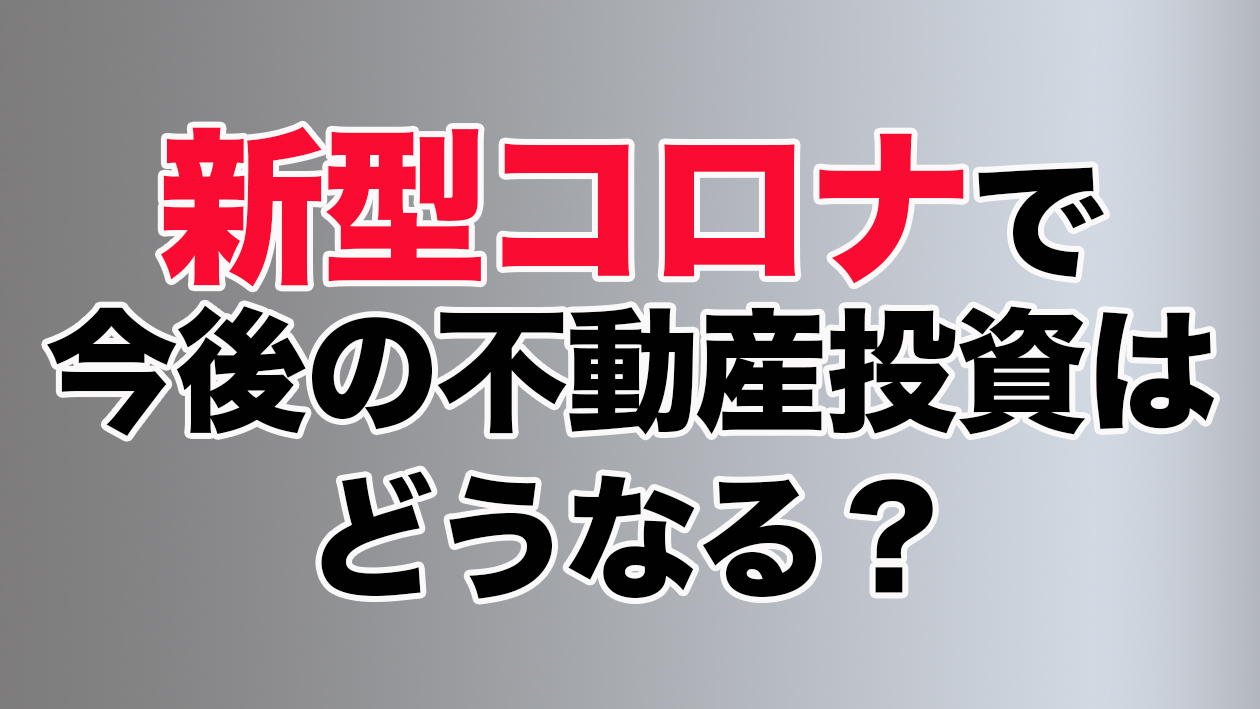株主優待を駆使して生活している方がいらっしゃいます。航空会社はチケットを半額で購入できる株主優待券を提供していますし、お菓子の会社は自社製品の詰め合わせが送られてきたり、自社のスーパーで使えるお買い物券やキャッシュバック券を提供していたりしてお得です。この記事では株主優待制度の概要、株主優待を受けるための方法、人気のある株主優待銘柄、実質0円で優待が受けられるクロス取引とその注意点について解説します。
株主優待とは?
株主優待は企業が株主に対して自社製品やサービスを割引して提供するなどの優待制度のことを言います。自社の株を買ってもらい投資をしてもらう、株主にはより長く株を保有してもらうという目的のために、株主になれば特別なサービスが受けられるようにして自社の株の魅力をアピールするための制度です。株主にとっては配当や値上がり益に加えて期待できる利益、恩恵のひとつと言えます。
優待の内容は、航空券の割引、自社製品の購入クーポン券やキャッシュバック券、自社製品の提供、など様々です。最近ではより長く株式保有してもらう目的で、長期の株の保有者には通常の株主優待にプラスして特別な株主優待を用意している企業もあります。
では、株主優待制度を受けるためにはどうすればよいのでしょうか?次に株主優待を受けるための条件について解説します。
株主優待を受けるためにはどうしたらいいの?
株主優待を受けるためには「権利確定日」にその企業の株主になっておく必要があります。権利確定日は銘柄によって違い確認が必要です。注意が必要なのは、証券会社で株を購入する際に株式の買い付けから受け渡しを受けて株主となるまでには2営業日かかるため、権利確定日の2営業日前の「権利付最終日」までに株を買い付ける必要があります。
2021年の6月を例に説明します。例えば6月30日(水)が権利確定日の銘柄があったとすると、6月28日(月)が権利付最終日となり、この日までに現物の株式を購入することで株主優待を受けることができます。ただし、その日の大引けまでに購入する必要があり、東京証券取引所の場合は15:00までに購入することが必要です。
翌日の6月29日(火)は「権利落ち日」といい、この日に購入しても株主優待を受けることができず、この日に株式を売却したとしても株主優待の権利はなくなりません。
株はどのくらい買えば株主優待をうけられるの?
株主優待を受けるためには最低必要な株数は企業ごとに決まっています。たとえばAという銘柄の場合は100株、Bという銘柄の場合は最低500株必要、などです。同じ企業でも株数によって受けられる優待が変わることが一般的で、例えば100株以上でお食事券1枚、200株で2枚、のように保有株式が多いほどもらえる優待が多くなるのが普通です。いくら優待の内容が魅力的でもそのために必要な株を買うための資金がたくさん必要であれば割に合いませんから、優待の内容と必要な株数、そして株価を確認して銘柄を選定することが必要です。
人気のある株主優待銘柄は
・すかいらーくホールディングス (2021年6月18日の株価1,567円)
| 自社グループレストラン株主優待カード 年に2回2,000円分(100株以上)5,000円分(300株以上)8,000円分(500株以上)17,000円分(1,000株以上) |
・日本マクドナルド (2021年6月18日の株価4,955円)
| 食事優待券 年に2回1冊(100株以上)3冊(300株以上)5冊(500株以上)※1冊中に「バーガー類・サイドメニュー・ドリンク」3種類の無料引換券が1枚となったシート6枚 |
・ヤマダホールディングス (2021年6月18日の株価509円)
| 優待券(500円券)お買い上げ金額1,000円(税込み)ごとに1枚、最大54枚まで使用できる500円分(3月)/1,000円分(9月)(100株以上)2,000円分(3月)/3,000円分(9月)(500株以上)5,000円分(1,000株以上)25,000円分(10,000株以上) |
このほかにもいろいろな優待があります。ご自分の生活の中で必要なもの、欲しいものがあるかもしれません。証券会社のホームページをチェックしてみてください。
実質0円で株主優待が受けられる!?-クロス取引
株主優待は魅力だけど、株を買って値段が下がってしまったら売ったときに損をするよね、という方もいらっしゃると思います。もともと株は優待を受けられるタイミングまでは株価が上昇し、権利落ち日以降は株価が下がる傾向があります。長期保有をするつもりの方は気にならないかもしれませんが、株主優待をもらえるタイミングに株を買い、優待を受けてから売却したい、でも値下がりのリスクはとりたくない、という方にはクロス取引というやり方があります。
クロス取引とは?
クロス取引は現物株を買うと同時に信用売りをする、権利落ち日以降に現物株の売却と信用売りの買戻しを行うことを言います。信用売りは証券会社から株を借りて売ることで、株価が下がったときに買い戻すことにより利益が出る仕組みです。
例えば今日株価が1,000円する株を借りて売却すると1,000円の売却益が出ます。次の日に900円になったと仮定すると900円で買うことができるため、買い戻しを行い、証券会社に返却します。この場合1,000円で売って返却のための株を900円で調達していることになり、100円の利益が出る、ということになります。これは空売りと呼ばれる取引のことで株価が下がっていても利益が出る仕組みです。
クロス取引は現物株の買いと信用売りを同時に行い、株価が下がったとしても信用売りの利益で現物買いの損失を相殺することで利益も損失も出ないようにする方法ということになります。利益も損失も出さずに株主優待をゲットすることができます。
クロス取引の盲点とは?
ただし、クロス取引にも注意が必要です。
・現物買いと信用売りは同時に行わないと価格差が生じて損をする場合がある
タイミングがずれてしまうと利益か損が出てしまいます
・信用売りには逆日歩(ぎゃくひぶ)とよばれる費用がかかることがある
信用売りは売り手が証券会社から株を借りることで、証券会社が持つ現物株が少ない場合、証券会社は生命保険会社等の機関投資家から借りて手当てをすることになっています。このときの株を借りるための費用が逆日歩です。逆日歩が生じるかどうかは前日の売り買いが終わった後でわかるため翌営業日以降に確定します。逆日歩の額については都度の入札で決まるため事前にはわかりません。売りを入れて買い戻すまでの日数分かかり、間に休日がある場合には休日分も支払う必要があります。例えば逆日歩が1株1日80円かかったという場合は100株で1日分8,000円、買い戻すまで3日あったとすれば24,000円かかることになります。お菓子メーカーの株主優待のお菓子詰め合わせセットを狙ってクロス取引をしたけれど、逆日歩発生で24,000円のお菓子を買うことになってしまいますから注意が必要です。
・配当がもらえない
現物買いには配当がつきますが信用売りの場合は逆に配当分を買い手に払う必要があるため、クロス取引をした場合には配当がもらえないことになります。
まとめ
株主優待制度の概要、株主優待を受けるための方法、人気のある株主優待銘柄、実質0円で優待が受けられるクロス取引とその注意点について解説しました。株価の上昇、配当にプラスしてもらえるメリットが株主優待。ご自分がよく利用するものや好きなブランドでもらえるものがないか探してみてはいかがでしょうか。