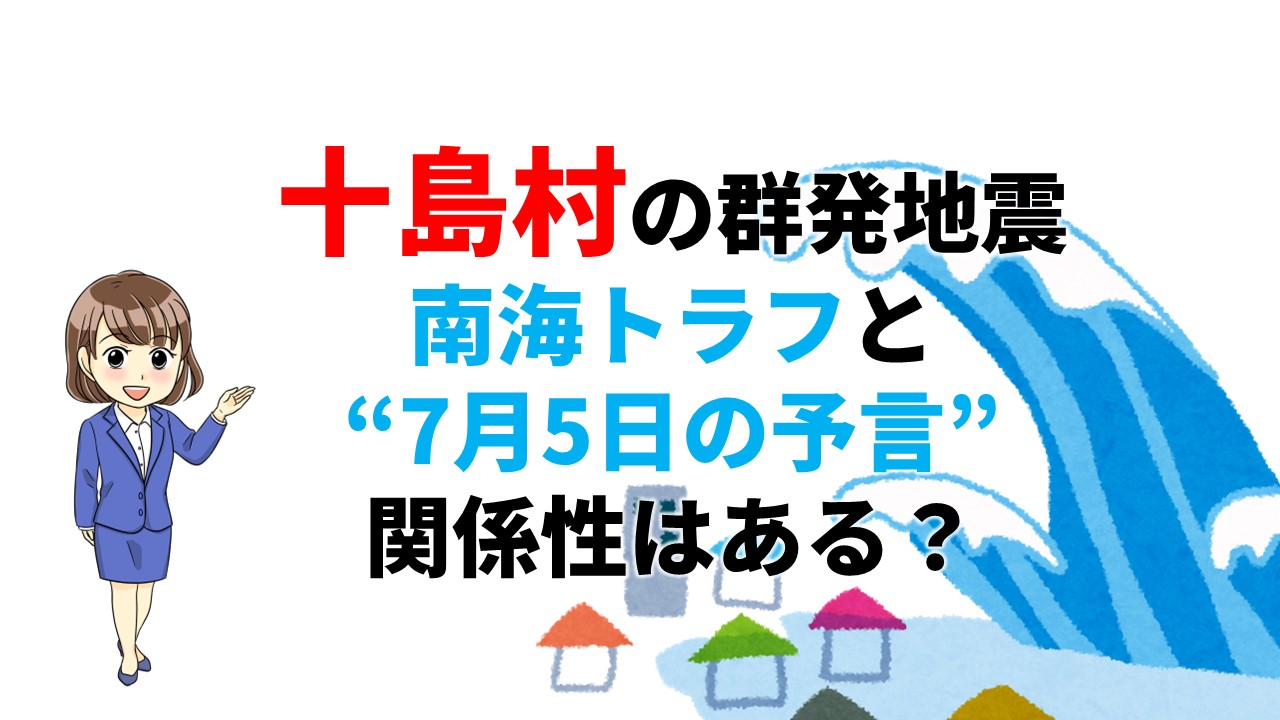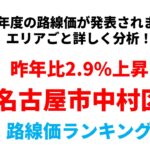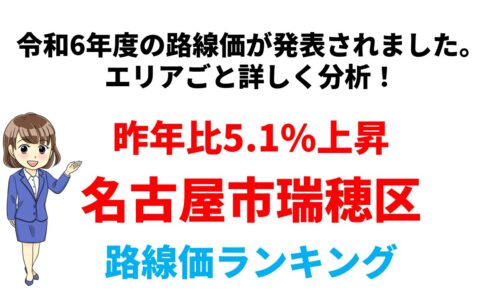2025年6月下旬から、鹿児島県の十島村・悪石島近海で群発地震が続いており、地域住民だけでなく全国的にも不安が広がっています。
さらにインターネット上では「7月5日に大災害が発生する」という予言めいた情報まで拡散され、不安を煽るような投稿が目立つようになってきました。
しかし、こうした“予言”の多くは科学的根拠がなく、専門機関も明確に「地震予知は現段階では不可能」としています。
不安に振り回されるのではなく、日ごろからできる備えを確実にしておくことが、最も現実的で信頼できる対策と言えるでしょう。
この記事では、十島村・悪石島における群発地震の概要と南海トラフ地震との関係、そして予言に対する冷静な視点と、いま見直すべき防災対策について解説します。
十島村(悪石島)の群発地震と南海トラフ地震との関係
まずは、十島村・悪石島近海で発生している群発地震の概要と、南海トラフ地震との関連性について詳しく見ていきましょう。
十島村・悪石島で発生している群発地震の概要
2025年6月21日以降、鹿児島県の十島村・悪石島近海で群発地震が続いています。
ピークとなった6月23日には、1日で180回を超える有感地震が観測され、地元住民の間には大きな不安が広がりました。
さらに、7月3日には悪石島で最大震度6弱を観測する強い揺れが発生し、建物の一部に被害が出たとの報告も出ています。
気象庁はこの一連の地震について、「地殻のひずみが原因とみられるが、海底火山や津波につながる異常は確認されていない」としています。
悪石島周辺はプレート境界に近く、過去にも群発地震が繰り返し発生してきた地域です。
今回も、期間中に数百回を超える地震が記録されており、「群発地震」としての典型的な性質を示していると言えるでしょう。
参考:NHKニュース
南海トラフ地震と今回の地震に関連はあるのか
南海トラフ地震の基本情報
南海トラフ地震とは、紀伊半島沖から九州沖にかけて延びる海底のプレート境界「南海トラフ」で発生が予測されている大規模地震のことです。
マグニチュード8~9クラスの地震が過去数百年ごとに繰り返されており、政府は今後30年以内に70〜80%の確率で再び大地震が発生するとの見込みを立てています。
広範囲にわたる強い揺れに加え、大規模な津波や火災、インフラの停止など多岐にわたる被害が想定されており、最悪のケースでは死者数十万人、経済損失は220兆円規模に達すると試算されています。
十島村の地震との関係性について
今回の十島村・悪石島近海の群発地震が、南海トラフ地震の前兆であるかどうかについては、多くの専門家が「直接的な関連はない」との見解を示しているようです。
その理由としては、両者の震源が異なるプレート境界上に位置していること、地震のメカニズムが異なることなどが挙げられています。
悪石島の群発地震は、地殻内の局所的なひずみによって発生するケースが多く、南海トラフのプレート境界型地震とは性質が異なります。
ただし、地震の予測は非常に難しく、地殻の変動が複雑に影響し合う可能性もゼロではありません。
そのため、関連性が「ない」と言い切れるわけではなく、あくまで現時点で科学的根拠が確認されていないという点に留意する必要があるでしょう。
「7月5日の予言」は信じるべき?
続いて、SNSなどで話題となっている「7月5日の予言」について、地震との関連性を踏まえながら解説していきます。
“7月5日の予言”とは?
2025年に入ってからSNSや一部の動画サイトなどで話題となっているのが「7月5日に大災害が発生する」という“予言”です。
この“予言”は、20年以上前に出版されたある漫画作品が出どころと言われており、過去の大災害の一部が漫画の内容と重なったことから、一部で「的中した」と話題になっています。
そして同作品内に「7月5日に噴火や大津波といった大災害が発生する」といった描写があることから、十島村・悪石島近海で群発地震が発生して以降「予言が当たるのではないか」と不安を抱く声が増加しているのです。
しかし、このような“予言”は解釈の幅が広く、特定の日付を示していたとしても、科学的な証拠や根拠に基づいているわけではありません。
予言に科学的根拠はある?
現時点の地震学では、地震の発生を「いつ」「どこで」と正確に予知することは不可能とされています。
日本の気象庁をはじめ、世界中の研究機関が「地震予知は技術的に実現できていない」と明言しており、過去に数多く流布された“地震の予言”が外れてきた事実からも、その不確実性は明らかです。
大切なのは予言の真偽を議論することではなく、災害が起こる可能性を前提に事前の備えをしておくことです。
とくに、地震大国である日本では「いつ地震が起きてもおかしくない」という前提に立ち、冷静に行動することが最も現実的で信頼できる防災対策と言えるでしょう。
いざという時のために、今できる備えを見直そう
ここからは、いざという時に備えるための基本的な防災対策を紹介していきます。
基本的な防災対策
災害時に最も重要となるのは、「今ある生活が突然止まる」という前提で備えることです。
とくに地震は予告なく起こるため、事前の準備がすべてを左右します。
いざという時のために備えておきたい代表的なアイテムは以下の通りです。
- 3日分以上の飲料水と非常食(レトルト食品、缶詰、乾パンなど)
- 応急処置用の救急セット(包帯、消毒液、常備薬)
- トイレ用の簡易処理グッズ(凝固剤付きの袋など)
- 軍手、マスク、ティッシュ、ウェットシートなど衛生用品
- 現金(ATM停止に備えて1,000円札や小銭も)
これらは防災バッグにまとめて、すぐに持ち出せる場所に保管しておくことが理想です。
地震による停電への備え
地震の直後には停電が発生するケースが多く、照明・通信・冷暖房の利用が制限されます。
とくに夜間の停電はパニックを招きやすいため、暗闇でも落ち着いて行動できる準備が重要です。
- 懐中電灯やランタン(電池式・手回し式)
- モバイルバッテリー(複数台あれば安心)
- ポータブル電源(医療機器やPC使用者は特に有用)
- LEDライト付きのラジオ(情報収集と照明を兼ねる)
スマートフォンは連絡手段にもなり、避難情報の取得にも欠かせないアイテムであるため、常に充電できる体制を整えておきましょう。
避難経路や連絡手段の確保
備蓄だけでなく、「いざという時にどう動くか」という行動計画も大切です。
- 自宅・職場・管理物件それぞれの最寄りの避難所を確認
- 家族やパートナーと安否確認の方法や集合場所を事前に共有
- 電話回線が混雑することを想定し、災害用伝言ダイヤル(171)やLINE・SNSの利用法も把握しておく
マンションやアパートに住んでいる場合は、非常階段や避難口の位置も日常的に意識しておくと、実際の避難時に役立ちます。
入居者の安全配慮(不動産オーナー向け)
不動産オーナーであれば、自身の備えに加えて、管理物件に住む入居者の安全も意識する必要があります。
- 共用部に落下物や倒壊の恐れがあるものがないか点検(看板、植木鉢、老朽化した外装など)
- エントランスや階段の非常灯・誘導灯の点検
- ゴミ置き場や駐車場まわりの安全確認(割れたガラスや瓦礫の危険)
- 入居者に向けた防災啓発(掲示板やポスティングで備蓄や避難所案内を告知)
万が一の事故が起きた際には、管理者責任を問われるケースもあるため、「何もない時」にこそ安全確認を徹底することが重要です。
まとめ
鹿児島県・十島村(悪石島)で続く群発地震や、「7月5日に大地震が起きる」という予言が注目を集めています。
しかし、現時点で南海トラフ地震との直接的な関連や、予言の科学的根拠は確認されていません。不確かな内容に振り回されず、防災用品の見直しや避難計画の確認といった「現実的な備え」を進めることが、最も重要な地震対策です。
地震はいつ、どこで起きてもおかしくありません。確かな情報と冷静な判断をもとに、いざという時に後悔しないための備えを行っておきましょう。